ニュースが出てからずっと楽しみにしていた一冊だ。
著者の中村隆之氏は早稲田大学の教授で、専門はフランスおよびカリブ海文学。アフリカ文化なんかもやっており、音楽系の著書としては『魂の形式 コレット・マニー論』という本をカンパニー社から出している。
ブラック・カルチャーというタイトルだけだとちょっと幅が広すぎるように感じられるが大西洋を挟んでアフリカとアメリカス(本書ではこのように表記される)、ヨーロッパとのの間で往還される黒人の文化について書かれたものだ。
基本的には合衆国の、それも音楽が中心に書かれている。
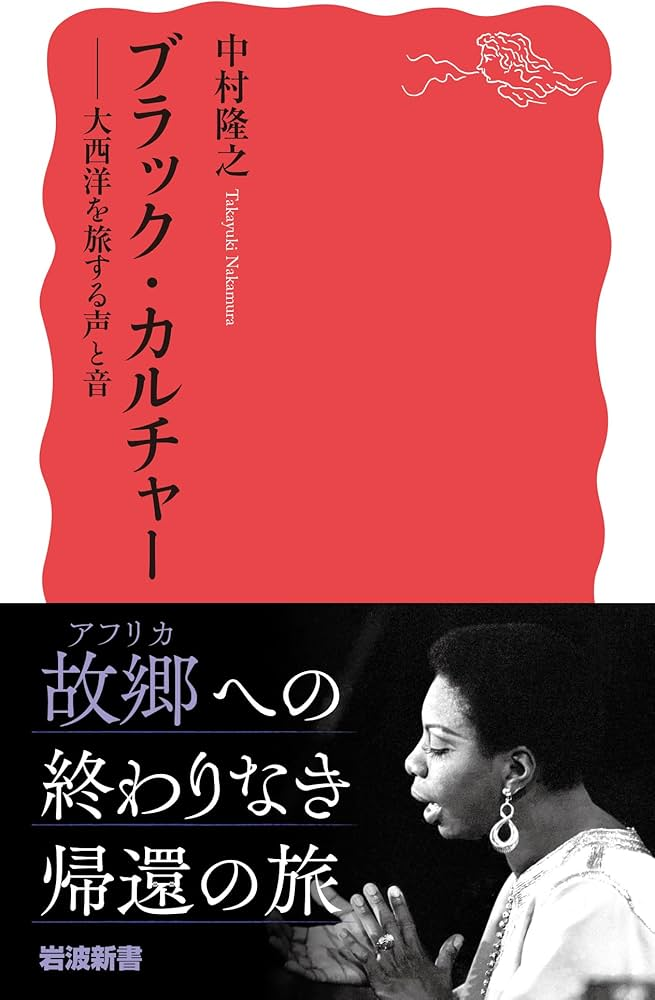
そもそもの起点としてのアフリカ文化の解説から始まる。決して無文字社会だったわけではないが、口承文化が基底にあること。マリ帝国が以下に豊かであったか。そもそもアフリカの中で行われていた奴隷のやりとり。
そこから新大陸へ送られる奴隷たちのさまざま形での抵抗。その一環としてその精神をさまざまな音楽の形態で伝えていったこと。スピリチュアルやシャウト、フィールド・ハラー。そこからゴスペルやジャズ、ブルース、ソウルなどが生まれていく。そこにはアフリカ由来の口承伝承の精神がある。これをアミリ・バラカに倣い「変わりゆく同じもの」と呼ぶ。
前半の6章はそういった形で新大陸でのブラック・ミュージックの展開の歴史が辿られる(レゲエやサンバなど中南米の音楽も含む)。
7章以降はもうちょっと各論っぽく、口承から文字へと形を変えて伝えられる奴隷時代の記憶、ブラック・パワーにまつわる思想(アフロフューチャリズムとアフロペシミズムなど)、21世紀に入ってからの音楽分野での取り組みなどが語られる。
コンパクトな中に膨大な情報が詰め込まれた力作で非常にためになる。ここに出てくる固有名詞から興味のあるところを拾って追ってみるといいんじゃないだろうか。
新書という分量の限られたフォーマットなのでしかたないとは思うんだけど、ハウス/テクノに触れられていないのは残念ではある。著者はぼくと同い年なので知らないはずはないんだけどな。
シャバカ・ハッチングスやムーア・マザーにも触れている上にビヨンセの近年の取り組みの話まで出てくるのだから、ビヨンセがハウスを取り上げた意味についてもわかってるだろうし。
あとは自分の趣味的なことだけどブラック・ムーヴィの話もあると嬉しかったなとは思った。
まあそういうのは言い出したらキリのないことだし、基礎資料として必読な本であることは間違いないです。
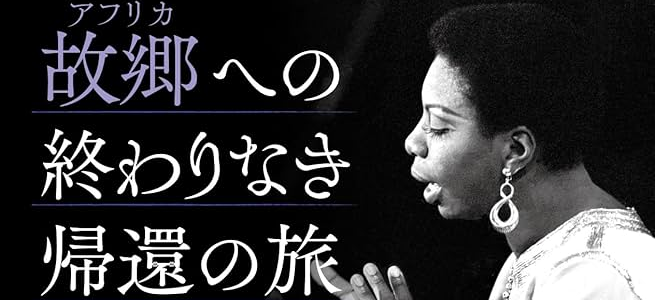

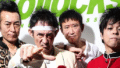
コメント