前回から、「芥川賞候補作の載っている文芸誌を一冊丸ごと読む」というのをやってみている。今回は候補が4作しかない。そのうえ、うち2作は同じ雑誌に載っているので楽だ。
ということで、まずは候補作2作掲載の「文學界」6月号。
芥川賞候補作は日比野コレコ「たえまない光の足し算」とグレゴリー・ケズナジャット「トラジェクトリー」。
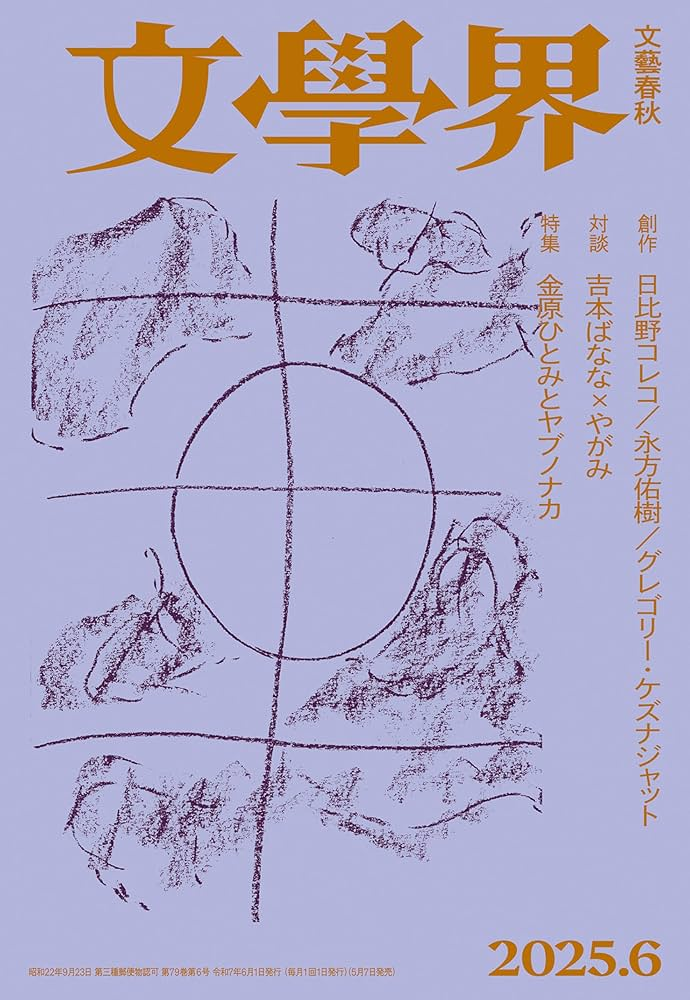
掲載順にまずは「たえまない光の足し算」。
主人公の薗は普通のものが食べられない身体になり、「異食道化師」として生きている。そこに出会う「抱擁師」のハグ、「軟派師」になろうとしているヒロメグ。ホームレスやそれに近い境遇の人々が大道芸みたいなことをして日銭を稼いでいる「時計台」や、黒いプールといった場所を舞台に展開される底辺的マジックリアリズムという感じだろうか。
「トラジェクトリー」のほうはそれに比べてオーソドックスなリアリズム小説。
主人公は名古屋で英会話学校の講師をしている。アメリカの大学を卒業し、なんとなく日本に来て特に目指すものもなく過ごしているうちに3年。講師の仕事の契約更新をするかどうしようか、悩むというほどでもなく迷っている。
やっかいな生徒(押しの強い中高年男性)とのマンツーマンレッスンでは生徒の持ってきたアポロ11号のレポートを延々と読む日々。
最後の節でちょっと時間が飛ぶのだが、なんか取ってつけたようなラストだなと思った。こういうのってわりといくらでも続けられるし、読む方もいくらでもそれなりに楽しく読み続けられちゃったりするので、終わらせ方が難しいんだろう。
創作は他にも載っていて、ひとつは前回の芥川賞で「字滑り」が候補になった永方佑樹の「生成変容体」。
タイミーで働きながらchatGPTと日々会話している主人公――というと、なんかすごい安易な感じがするが、主人公が実践している「内語の反芻」などを通して言葉についての小説になるところはこの著者の関心が一貫していることはわかる。
もう一編は2025年上半期同人雑誌優秀作として掲載の岡本千尋「誰そ彼のあわいに」。
主人公は終末医療で死にゆく患者の話を聞く「傾聴ボランティア」をしている。死期の近い服役中の犯罪者から話を聞いてほしいとリクエストを受ける。患者は父親を殺した女性だった。
そこまでびっくりするような話でもないのだが、この号ではこれと「たえまない光の足し算」が面白かったかな。
金原ひとみの新作『YABUNONAKA』が特集されていて対談や書評が掲載されているのだが、面白かったのは人生相談コーナー。作家たちが金原ひとみにいろいろな相談をしているのだが、回答がなかなか見事。特に阿部和重のは相談も回答も最高だった。
鴻巣友季子の国際ブッカー賞と海外で翻訳される日本文学についてのエッセイもためになる。忘れがちなのだけど、まずブッカー賞と国際ブッカー賞は違う。そして後者は翻訳作品に与えられる賞である。そういえば鴻巣さんは王谷晶受賞の際にも訳者名が記事にならないことを批判していたな。
英語圏で近年、外国文学の翻訳が進んでいること。その背景にあるのは保守主義・排外主義の高まりに対するカウンターなのではないかと指摘。
また日本語訳にもあることだが読みやすさに関する問題。英語圏では編集に近いことをすることが多く、村上春樹作品なども英語版ではかなり変わっている。
そもそも英語圏の読者は翻訳を読むこと自体が嫌いなので、なるべく翻訳だとわからせないような本の作りになっているのだそうだ。それにともなって起きるのが翻訳者の地位に関する問題で、訳者名が表紙に載らないケースが多いという。
一方で近年注目の翻訳者としてポリー・バートンという人物を挙げている。日本の現代文学、特に女性作家の作品を多く訳しており、その多くが注目されている。最近では金井美恵子の評価が急激に上がっており、ノーベル賞候補と言われるようになったり。
人気分野としては ・犯罪、シュール、癒やし、ディストピア。それにフェミニズムを合わせたものが強いという。といったことから今後のスター候補として挙げられているのが柚木麻子(『BUTTER』が海外で爆発的に売れているのは有名だろう)。たしかに今回の王谷晶『ババヤガの夜』もその路線なので納得はいく。
その他、細かい記事では北村匡平エッセイが面白かった。藤井風の推し活で家庭が円満にという話。

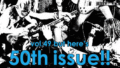
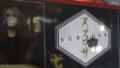
コメント