1巻を7/1に読み終え、7/22に2巻を読了。だいたい一日20ページのペースで読んでいき、最後に残り少なくなったら一気に読むという『失われた時を求めて』と同じスタイルで臨んだのだが、分量的にプルーストの5分の1くらいなので、やはり5分の1くらいの期間で読み終えたのだった。
1巻のときにも書いたかもしれないが、なんで『魔の山』を読もうと思ったのかというと『失われた時を求めて』との共通点があるからだった。サナトリウムを舞台とした長編で、執筆時期も近く、間に第一次世界大戦を挟んだことが作品に大きな影響を与えているということ。
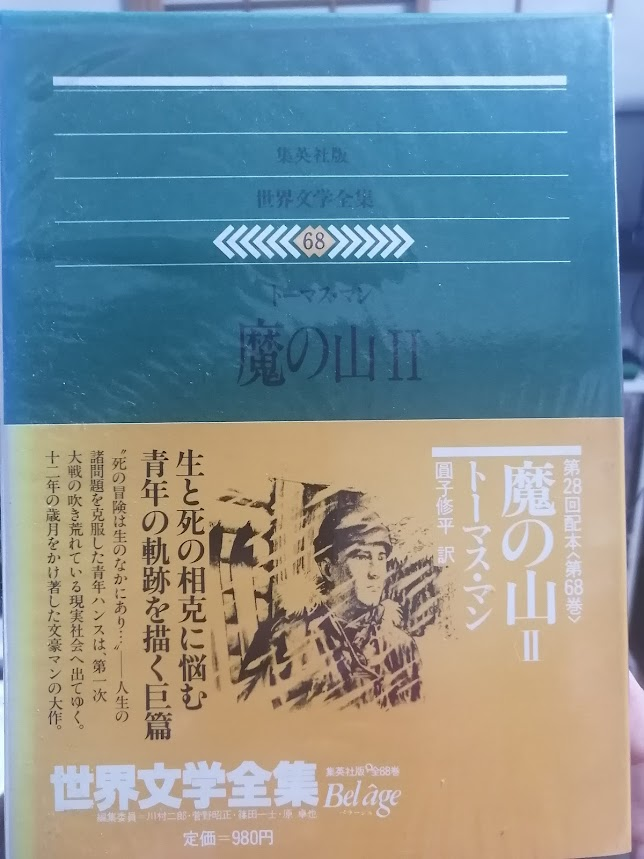
前作の最後にファム・ファタール的なロシア人の人妻ショーシャ夫人と何かあったのかなかったのか、なんて一晩があった後、その人妻はさっさと山を降りてしまう。
残された主人公は、本来は従弟の見舞いに来たはずなのに自分も具合が悪いということで長期滞在に入る。挙げ句の果には従弟は軍隊に戻るといって山を降りるのに、自分はショーシャ夫人がまた戻って来るかもしれないと思って山に残ることを選択する始末(ほぼ治ってるのに)。
2巻で登場するナフタという人物がまた強烈だ。前巻から引き続き登場する人文学者のセテムブリーニの論的としてテロリズムを擁護する過激な論陣を展開する。二人の激論は『失われた時を求めて』に出てくる議論の数々と比べてもガチ度が高く、最後は決闘にまで至る。
ショーシャ夫人はやがてペーペルコルンというなんだか大物っぽい人を愛人にして再登場する。この人物が地獄の黙示録のマーロン・ブランドみたいな変に強い影響力を持ち、サナトリウムを半ば支配するような状態になるも、すぐに死んでしまう。
ハンスのサナトリウム滞在は、1巻の冒頭で示されたように7年に及び、ラストでは兵士として戦場に赴く。
なにか夢の中のような独特の時間が流れる山の上の世界と、最後の戦場の場面のあまりの違いも印象的だった。
100分で名著でも最近本書が取り上げられており、ニーチェの影響や当時のドイツ社会の雰囲気が反映されていることが指摘されていた。
結論としてはプルーストとはだいぶ読後感は異なる。このへん、フランスとドイツの違いなのかなとか、さらに言うならばドイツの方はこの時点でナチスへの萌芽が見えるのかもしれないな、なんて思ったのだった。
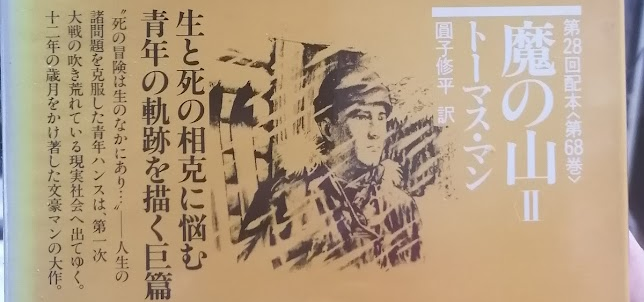


コメント