先日、箱根のポーラ美術館に行った際に、古新聞・古雑誌を模した陶芸の作品があった。新聞の紙面やマンガ雑誌の表紙などが表面に描かれ、紐で結ばれて資源ごみに出されようとしているもののようになっているというものである。
前にも別な美術館で観た記憶のあるもので、すぐに「あっ、これ見たことある」と思ったのでそれなりなインパクトがあったんだろう。
これは現代陶芸作家の三島喜美代による作品で、70年代からこのスタイルでやっていた方のようだ。

現代美術における陶芸というものについて、特になにかイメージを持っていたわけではないんだけど、ちょうど図書館で借りてきていた「美術手帖」の前号で「現代の陶芸」という特集が組まれている。
(図書館に蔵書されている「現代思想」「現代詩手帖」のバックナンバーを全部読むというプロジェクトに取り組んでいるのだが、ついでに「美術手帖」の最新号も読んでいこうと思ったのである。本当の最新号は貸出不可なので実際に読むのはひとつ前の号になる)
どうも近年、陶芸への注目が高まっているのだそうだ。
そもそも器/オブジェという対比があって、これはクラフト/アートという対比でもある。アートがクラフトを下に見るみたいな風潮があったんだけど、近年はその対立軸を超えるようなものが出てきているらしい。
そもそも日本は近代化にあたって自国の文化として超絶技巧的な焼き物の技術をプレゼンしていこうとしてたんだけど、実際にはそのオリジナルは中国にあるということがすぐにわかってきてしまい、逆に茶道とかで言われるちょっといびつなものに美を見出すという方向性に向かう。なんだけど、それは陶芸作家側が意図してやることではなくて、打ち捨てられたようなものに茶人が価値を認めるというところに意義があるわけなので、その方向は難しい(しかも茶人たちがそういう方向の美を見出したのはもともと朝鮮の茶器だったとか)。
一方でクラフトのほうに価値を見出した人たちは民藝運動のほうに行く。それと合わせて「オブジェ」としての陶芸路線である前衛陶芸というのがある。だいたい近代以降の陶芸というのはそんな流れだったようだ。そんな中で21世紀になって現代美術方面から陶芸へのアプローチがあったりしたと。
巻頭では特に現在注目を集めている作家が豊富な写真とともに紹介され、その他作家名鑑みたいなのも充実。いまの陶芸ってすげえんだなあという素朴な感想を抱く。
主要な技術・技法の紹介なんかもあってなかなかためになる。
あとはダンス公演についての岡田利規インタビューが歯に衣着せぬ感じで面白かったり、椹木野衣が橋の下世界音楽祭を紹介していたり。

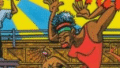
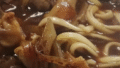
コメント