ここ3年ほど、ゲンロンカフェで年末に行われている斎藤哲也・山本貴光・吉川浩満による「人文書めった斬り!」イベントに参加している。
毎月何百冊という単位で本を買う人たちがその年に出た「人文書」(ここではかなり広義)を振り返り、「大賞」を授与するという催しである。
2023年の同イベントで最大のインパクトを与えたのが岩波書店の『関孝和全集』だった。全三巻をセットで箱入り、お値段税込2万7500円! 当日、会場では本の値段を測る単位として「0.05タカカズ」といった新たな単位が爆誕したのだった(東京ドーム◯個分みたいなやつ)。
ぼくは浅学非才なのでその場で初めて関孝和という名前を知ったのだけど、この特集を読んでようやく日本数学史の最重要人物といっていい存在だったということがわかった。この号がでたのは2021年なので、別に全集の刊行と合わせたわけではない。なんでこのタイミングで特集されたのかは不明。
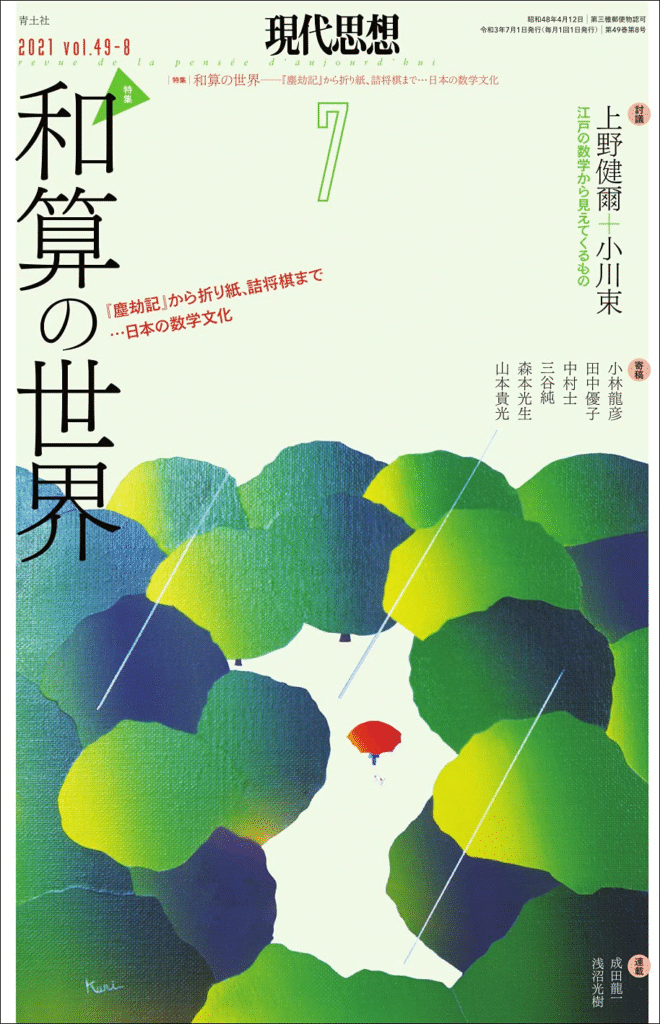
関と建部兄弟の共著による大著『大成算経』。それ以前にポピュラー数学の普及に寄与した「塵劫記」や、「算額」と呼ばれる絵馬みたいなものを用いた投稿バトル(20年以上にわたって激論がかわされるトピックもあったとか)といった江戸時代の庶民たちの数学カルチャーとその背景。明治期における「洋算」の導入と度量衡の統一等々、知らなかった話がたくさんである。
ちなみにゲンロンに「関孝和全集」を持参した山本貴光さんももちろん寄稿している。江戸時代の算術者をゲームで表現するには?という楽しいエッセイだ。
といった感じで知らなかったことがたくさん載ってて楽しい特集なのだが、一方で和算史・数学史も含めて「◯◯学史」という分野の難しさなども語られる。数学史ひとつとっても、数学に興味がある人と歴史に興味のある人での断絶があり、たとえば大学においても理系の学部でやるのか文系の学部でやるのかといった問題が起きる。素人考えでは両方の立場から知見を持ち寄って協力し合えばよさそうなものだと思ったりするのだが、まあ難しいんだろうね。
ともあれ、今年は「図書館に在庫されている『現代思想』のバックナンバーを全部読む」というプロジェクトに取り組んでいるのだが、それはこういう特集に出会うためにやってるのだと言っていい。普通にしてたら絶対手に取らないようなものを読んで、しかもそれが面白かったりすると、やってよかったなと思うのである。
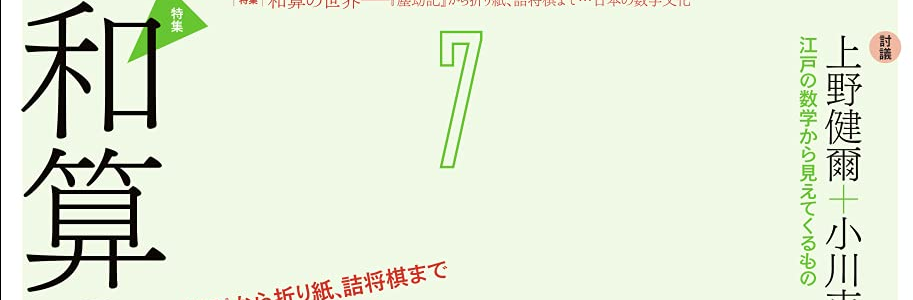

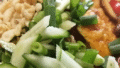
コメント