一年で大きくカルチャーが変動する時期というのがある。
60年代ロックを聴いていると、とにかく1~2年の間に一気にサウンドが変わっていくので驚かされる。64年と65年ではだいぶ違うし、67年と68年の違いもたいへんなものだ。
明治期の文学というのもそういう時代だったのかもしれない。
先日、二葉亭四迷の『浮雲』を読んだわけなんだが、これは坪内逍遥の『小説神髄』および『当世書生気質』の批判として書かれたものだという。
ちょうど我が家にその『当世書生気質』があったので読んでみたという次第。
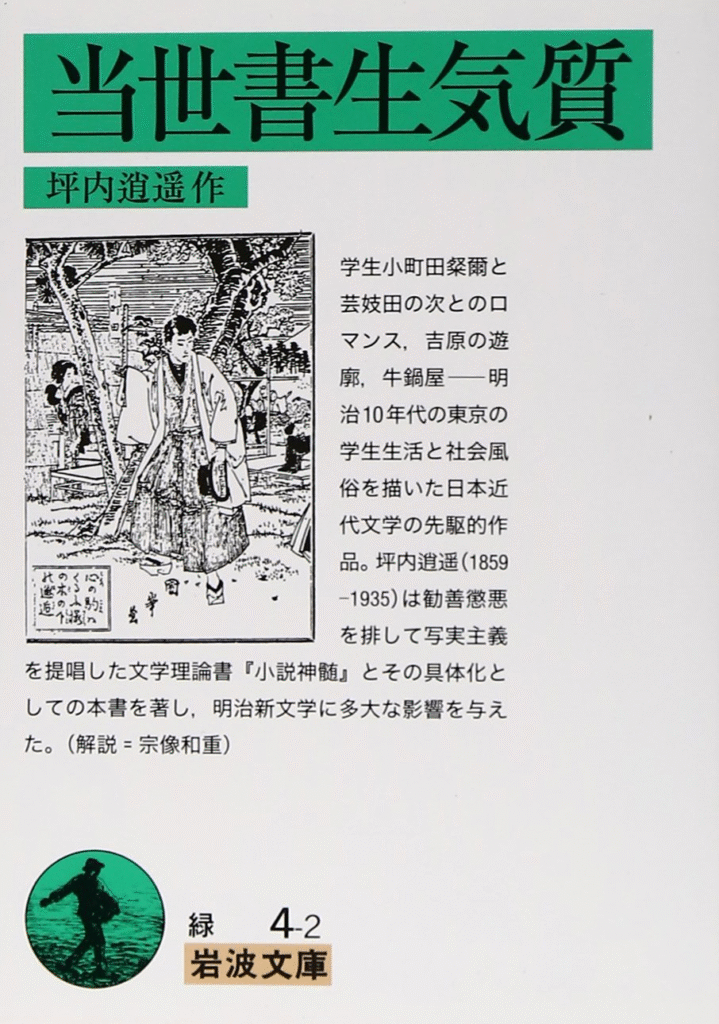
『小説神髄』は未読なのだが、同書で主張された小説の主眼とは勧善懲悪ではなく、「人情」を写し取るにあるという理論の実践として書かれたのが『当世書生気質』なのだという。
生き別れの兄妹というのをメインのストーリーに据えつつ、当時の書生たちの生活を描写することが主眼になっている。
書生の生態がもっぱら飲み歩いて遊郭に繰り出しては門限を破りみたいなことばっかりなので、刊行時には批判もあったりしたようだ。批判に対する著者のコメントが挟まれるのだが、そこでも小説とは下流の生活と人情を描くことが主眼なのだという自説を述べてディケンズなんかを例に挙げている。
で、『浮雲』と比較してすぐに目につくのは文体の古さである。まあ普通に古文。ちょっと河端一さんのブログを彷彿とさせたり。一方で台詞はわりとリーダビリティが高い。というか読んでて面白いのは台詞だったりする。
なにが面白いってカタカナ語の異常な多さ。たとえば金のことを「M」(Money)と言うんだけど、これは当時の学生たちの隠語みたいな感じなのかね。
あと遊女を「プロ」っていうのだが、まあ玄人ってことかなと思うと「プロスティテュート」のことだったりする。
それ以外にもやたらとルビで「泥酔漢(ドランカアド)」だの「吉原(グウド・プレイン)」だの「我が輩の時計(ウォッチ)では十分(テンミニツ)ある」だの。ほんとにこんな言葉遣いだったのかはわからないが、まあ読んでて楽しい。
会話は軽妙なんだが、吉原とかがたくさん出てくることもあって、なんとなく落語を読んでるような気になってくるのだが。でも実際に落語の書き下しを文体の参考にしたのは『浮雲』のほうだったりもする。
台詞は楽しく読める一方で地の文は古文なのでギャップが激しいのだが、それにくらべて『浮雲』は、普通に読める。『当世書生気質』が1885~1886年刊、『浮雲』が1887~1890年と考えると、この差は大きいなと改めてびっくりする。
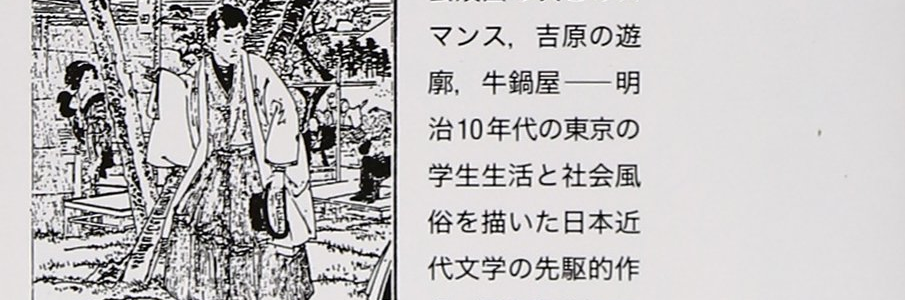
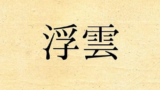
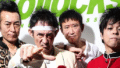

コメント