長谷川二葉亭は日本近代文学を作った人物である。
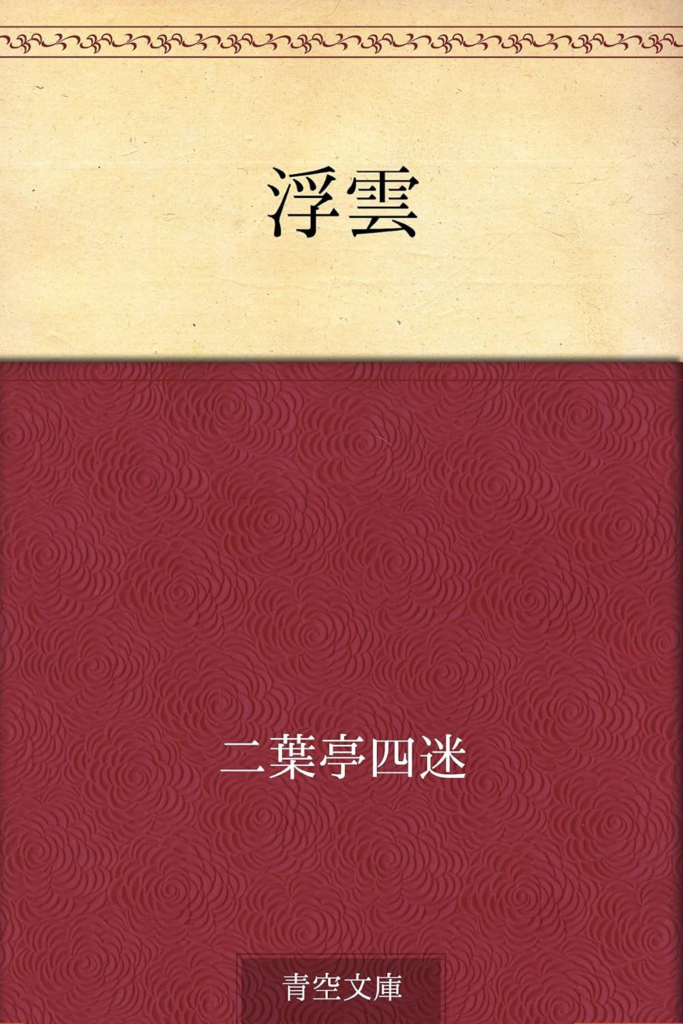
『浮雲』といえば「言文一致体」を初めて導入した小説だというのが文学史における定説だ。実際に読んでみると、普通に読めるので驚く。もともと落語の速記を参考にしたと言われてるだけにリーダビリティは高い。読んでいくうちにだんだん文体が変わってくるのも、試行錯誤の跡が見られて興味深い。第一編から第三編まで三年くらいかかってるし。
ちょっと特徴的だなと思うのは、「~で。」という語尾が多用されているところで、このあたりはいまの文章よりも口語的なのかもしれない。
文体だけでなく内容的にも先駆的である。
叔父の家に下宿している青年、文三が下宿先の娘に懸想しているが、役所をクビになり、叔母さんからさんざん馬鹿にされる。ライバル的な友人の本田は軽薄ながら要領の良いタイプで出世もするし叔母さんにも気に入られていく。焦りながらも文三は本人の意固地な性格もあって本田に頭を下げることもできず、叔母や娘とも険悪になっていく。
あらすじだけ見ると昼メロみたいだし、これをシリアスにすると漱石の『こころ』みたいになっていくのかなという気もする。
四迷自身はこの作品に納得がいかず、この後20年くらい小説を書くのを辞めてしまう。そもそも本作の第三編冒頭にも「固と此小説ハつまらぬ事を種に作ッたものゆえ、人物も事実も皆つまらぬもののみでしょうが、それは作者も承知の事です。」などと書かれているのだが、近代文学の文体を作ることはできたものの、ロシア文学に親しんだ四迷にとってそれにふさわしい「内容」を見つけることができなかったということらしい。
後年書かれることになる『平凡』を読むとそのあたりの感じがわかる(ぼくは高橋源一郎が絶賛してたので『平凡』を読んでこれはたしかにすごいと思いつつ、肝心の『浮雲』はいままでずっと読まずにいたのでした)
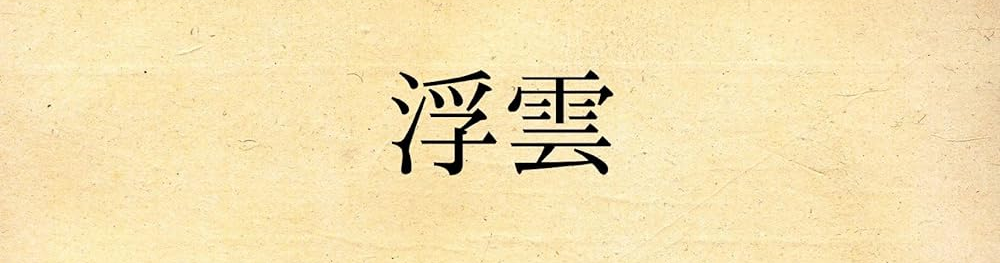

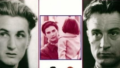
コメント